「正しい戦争」は本当にあるのか
(インタビュー 渋谷陽一・鈴木あかね)
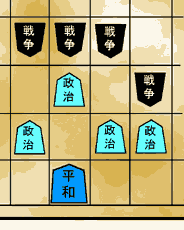
きれいな戦争、きたない平和
戦争をめぐって二つの立場がある。ひとつは「正義の戦争=秩序を壊す国は倒すしかない」。もうひとつは「絶対反戦=
武器よさらば、ラブ&ピース」。藤原はどちらにも同意しない。「国際政治のリアリズム」という立場から、戦争が起こる政治の現実、平和が保たれる政治の現実、その両方をあくまで直視する。
藤原の「リアリズム」では「正義の戦争」への批判が甘くなるわけではない。むしろ鋭く幅広い。戦争をなんとか飼いならしてきた国際ルールをブッシュ政権は完全に踏みにじった。また「正しい戦争」などという発想は欺瞞であるうえに、欲得の戦争に増して最悪の惨状を生じさせる。そうはっきり非難する。だから日本のアメリカ追従も違憲どころか空前の愚行だと呆れる。これらを強調するため、三十年戦争、ナポレオン戦争、世界大戦などを経て戦争という手段がどう戒められてきたかを示し、その長い英知をイラク戦争が覆してしまったと断罪する。また、冷戦の終結が「米ソの緊張緩和」をもともと意味していたのに、湾岸戦争とソ連崩壊のなかで「アメリカの勝利」という誤解へと変質し、そのままアメリカと武力の賞賛という流れを決定づけたとも指摘する。このほか、国家秩序の根拠が「力」から「民族」へさらに「デモクラシー」へと推移した功罪を分析し、デモクラシーの普遍性は認めたうえで、アメリカは世界を民主化などしていない、民主化は国内の反政府運動なしには実現しない、との認識を崩さない。
そうではありながら藤原は、理念だけの「絶対反戦」にも与しない。戦争をなくすことは目標だが、それには武器に頼らないですむ緊張緩和の状態をまず作る必要がある。どんな機構やプロセスならそれが進むのか。そうした「リアリズム」に基づく実践しか評価しない。《何度も言いますけど、平和っていうのはそんな観念よりも具体的な、目の前の戦争をどうするか、戦争になりそうな状況をどうするかって問題なんです。平和主義を守るか守らないかってことよりも、具体的な状況のなかで平和を作る模索が大事だって思ってます》。
日本特有の平和主義についても、憲法9条と日米安保の矛盾や自衛隊の扱いを曖昧にしてきた怠慢を当然ながら突く。しかも馬鹿げたことに、この平和主義が、空論であるだけならまだしも、紛争に直面して立ち往生し思い余って戦争主義に反転したのが今の日本だという。その不可思議な事態とはこうだ。《日本は〈平和〉という色眼鏡をもって世界を見る状態から、一転して軍隊に対する希望的観測でものごとすべて見る方向にひっくり返っちゃったんですよね。軍隊なかったら平和になるんだっていう極端な平和主義が裏返しになったみたいなね。世の中は危ないんだからガツンとやるしかないっていう。これは逆の軍事崇拝みたいな感じで、教条的ですよね》。《…憲法をベースにした平和主義があまりに実情と離れてしまったため、逆に軍事力に対する過度の楽観主義が広がっちゃった》。現実を見ない絶対平和から現実を見ない絶対戦争へ。具体性と実践のリアリズムを欠いたツケがとうとう回ってきたのか。
つまるところ、平和とは、お題目でなく、作り出すものだと言う。この本全体がその実例・試案集と見てもいいだろう。とりわけ北朝鮮への対応を語った最終章は、難易度の高い「リアリズム」演習だった。我々には他人事ではないし緊迫性もあろう。ここで藤原は、東アジアは欧州と違って冷戦の終結が不完全であり社会主義や軍事的緊張が残った地域であることに注意を向ける。したがって人権や民主主義といった理念に支えられた平和は難しく、安全保障のための伝統的な外交が求められると説く。そのうえで、北朝鮮はイラクと比較にならない脅威であり、解決にはアメリカの武力による抑止が不可欠だと認める。それでも武力によって外から政府を倒すことには慎重な姿勢を貫く。そしてやはり六カ国協議が危機を打開する唯一の道と見る。ただしそれは「話せばわかる」という気楽なものではない。アメリカの抑止によって攻撃の手を縛り、地域協力によって各国との個別取り引きも封じる。そうやって北朝鮮のオプションを絞ったうえで、交渉による解決を探る。こうした粘り強い綱渡りにこそ、平和を生み出す「リアリズム」があるのだろう。別の章からだが、次の引用を改めて噛みしめたい。
《現実の分析っていうのは、目の前の現象をていねいに見て、どんな手が打てるのかを考えることです。そのとき、すぐ兵隊を送るのは短絡的です。伝統的な外交というのは、武器を手段としながら、外交交渉、悪くいえばボス交渉と談合によって自分に有利な条件を獲得するってそういう取り引きでしょ。だけど、原則として平和を掲げて国際政治を見てきた人たちってのは、今度は国際関係の力の現実とかいうものにぶつかると、なんというか教条主義的な平和主義者、あるいは教条主義的な戦争主義者になっちゃうみたいです。いまの日本で起こっているのはそういう状況でしょう。だけどそれは事実に即していないんです》。
《一言いっておきたいんですけど、平和って、理想とかなんとかじゃないんです。平和は青年の若々しい理想だとぼくは思わない。暴力でガツンとやればなんとかなるっていうのが若者の理想なんですよ。そして、そんな思い上がった過信じゃなく、汚い取り引きや談合を繰り返すことで保たれるのが平和。この方がみんなにとって結局いい結論になるんだよ、年若い君にとっては納得できないだろうかもっていう、打算に満ちた老人の知恵みたいなもんです。そういうことをね、伝えていきたいんです》。
本の紹介はこれくらいだが、なお個人的に気になること。
藤原は、紛争解決の手段としての武力を完全に放棄することは難しいと考えている。《えーっと、平和論に水をかけるような言い方になりますけど、軍事力の行使の必要な場面が国際関係にあるかないかといえば、残念ながらあるというのがぼくの考え方です。ナチス・ドイツの問題もそこにあるわけで、ほっときゃいいとはぼくには言えない。軍事力で対抗するほかに方法のない状況があることは否定できない。その意味でぼくは、絶対平和論者じゃありません》。同書全体からも、特定の地域や情勢に限るなら、平和のために武力を使うことが政治の本性であり政治の知恵でもありうる、と考えていることが窺える。
これはなかなかもどかしい。
同書のタイトル「正しい戦争は本当にあるのか」という問いを、藤原帰一は主に「ブッシュの正義の戦争は認められるか」という意味に受けとめ、そのような正しい戦争などありえないとしている。「戦争をしかねないイラクという悪い国やフセインという悪い奴に対する戦争だけは正しい」というブッシュ政権の発想を、断固拒否したわけだ。
そうするとしかし、こう問いたくもなる。――アメリカの正義の戦争は「正しくない」ということですが、藤原さんが認める紛争解決のためにどうしても行使せざるをえない武力だけは「正しい」と言うべきなのでしょうか。それだけはもはや反対できないのでしょうか、と。渋谷陽一らが「正しい戦争は本当にあるのか」と尋ねたのは、もとはそういう意味だったともとれる。
受け入れざるをえないと認めても、なお受け入れがたいという気持ちだけは別にある。あるいは、自らがその武力を被ることだけはどうしたって受け入れがたい。こうした背反する気持ちをどう処理したものか。「絶対反戦」は理念だけで実践を伴わないと批判された。しかし「絶対反戦」の動機には、このような問いも含まれているのではないか。
藤原はなにより「正義の戦争」の愚かさを立証しようとする。「絶対反戦」はあえて深追いしない。だから上のような問いに向き合うことはない。このような問いは、また別次元の問いなのかもしれないが…。
*
もうひとつ気にかかること。藤原の「リアリズム」からすれば、個人が「ラブ&ピース」と叫んでも紛争解決に向けた実践としては無意味ということになる。《たとえばいま、イスラエルやパレスチナに行って、軍隊なくしなさいと言ってもまともに聞いてもらえないでしょ》と。そうすると、イラク戦争や北朝鮮との緊張に対して、交渉や提言の役割を担っている外交官や政治家、政治学者でもないかぎり、個人はまるで関与できないのか。ちょっと虚無感が漂ってくる。「なんかラブ&ピースってダメらしいぜ」「でも、それってピースがウチらと関係ないってことでしょ」「あ、そうか。じゃあラブだけで!」
渋谷には「絶対反戦」の立場を捨てきれないところがある。だから「ラブ&ピース」とやや自虐的に呼ぶものの、その役割をさらに問う。藤原はあまり乗ってこない。ただその代わり、イラク戦争などに対する日本人の本心を抉ろうとする。世界は今、先進国とかけ離れた地域を放置し、砲火もそこに集中している。おかげでイラクは戦争中でも一般の日本人が死ぬことはない。しかしそれは同時に日本人から戦争のリアリズムを遠ざける。戦争に踏み切るにも理念しかない、と。
《この議論の前提にあるのは、自分たちが被害者になる可能性が少ないということですよ。その紛争の展開によって本当に自分たちが被害者になるとすれば、戦争について間違ってもそんなタカをくくった言い方なんかできないわけですよね》。
戦争に関するリアリズムの欠如が、戦争への無責任そして無関心を生んでいる。しかしこの現象は、繰り返しになるが、そもそも日本人が幸いにも身近で戦争を体験せずにすんでいるという、もうひとつのリアリズムに由来している。皮肉だ。戦争のリアリズムは、犠牲の当事者でなければ持ちえないのか。
加えてもうひとつのリアリズム。冷戦とは米ソ対立・東西対立という大きな緊張だったが、なぜか大きな戦争にならずに終結した。そのため過去の大戦争に比べて戦争に対するアレルギーもまた生じなかったと藤原は言う。アメリカ単独の武力戦略が容認される状況はそこから生じている。そうなると、世界が本気で武力を放棄するには核戦争が起こるしかないのでは、とまで考えは進む。
戦争に対して誠実に正確に対処しようとする姿勢は、自らが犠牲を被らないかぎり、あるいは過度に悲惨な状況にならないかぎり、確立できないものなのか。
これに並ぶ厳しいリアリズムが、別のところにも垣間見える。世界の最貧層は、実はテロリストにすらなれないというのだ。あるいは、貧困という問題は攻撃によってしか気づかせることができないと。
*
いくつか挙げてきた事例は、どれも似たような虚無感を運んでくる。では、そんなところで「ラブ&ピース」と叫ぶのは、ただの能天気なのだろうか。そうとばかりは言えまい。国家による戦争と平和という少しもきれいでないリアリズム。最小限の武力(とその武力を被るはずの他人の犠牲)は容認せざるをえないというリアリズム。それに対してオレは何もできないというリアリズム。そうしたリアリズムを知らない者だけがイラク戦争に無関心になるのではない。いやというほど知っているがゆえに無関心としてやりすごすところもあるだろう。武力を完全には放棄できないリアリズム、それに無関心にならざるをえないリアリズム、どちらも避けられないと知りつつ、どちらも耐えられないという思い、それが人をたとえば「ラブ&ピース」に向かわせる。「ラブ&ピース」はそんなリアリズムを含んでいるのではないか。
ところで、この本の前に私は稲葉振一郎『経済学という教養』を読んでいた。その分析によると、左翼はマルクス主義の理念で資本主義に抗してきたが、不況という現実を前になぜか熾烈な市場原理主義へと急転回し、それが小泉内閣の構造改革を後押ししているという。(参照:本の感想)
どうだろう。理念先行だった日本の平和主義が、イラク戦争や北朝鮮という現実を前にして、あれよあれよと戦争OK・戦争第一に傾いてしまった様相と、あまりに似ている。
伊達や酔狂じゃすまない現実がいよいよ迫り、初めて正面からぶつかって、転ぶ。どうもこういうところに、日本の政治や経済の現在地があるような気がしてきた。
*
さらにいうと、『経済学という教養』は、市場経済に代わる現実のシステムはありえず、そこで共存共栄の属性として最小限の不平等が生じることは容認するという立場だった。これもまた、紛争や緊張という現実が完全には避けられず、そのため最小限の武力は認めせざるをえないという藤原の立場と、みごとに符合する(まあいずれも常識か)。それでも「いかに合理的であれ不平等は絶対いやだ」「いかに合理的であれ武力行使は絶対いやだ」とそんな思いが、やはり同じく残る。これは問うてもせんないことなのか? それはまた改めて考えよう。
「戦争反対!」なんて意気込むと「あなたは現実を知らないね」と諭される。たしかによく知らないので言い返せない。そうか現実を前にしたら平和は諦めるしかないのか、と。ところがその現実をしっかり見つめてみると、戦争だ戦争だと意気込む連中だって現実をよく把握していないことがわかる。しかしいっそう思いがけないことに、平和への空論は、戦争への空論と同じくらい大きな過ちに転びかねないのだ。『「正しい戦争」は本当にあるのか』は、戦争をめぐる政治の力学を冷静に丁寧に平明に解き、こうした図式に気づかせる。藤原帰一は「戦争は絶対避けられる」と楽観はしない。だが「戦争は絶対避けられない」と悲観もしない。そして平和という細道を理念よりも実践の課題として探っていく。戦争の可能性は0%でも100%でもなく、常にその中間を揺れ動いてきた。そうした政治と歴史の現実が次々に示されて、目から鱗も次々落ちる。最終的に私はこう励まされたように感じている。諦めるべきは平和じゃない、戦争のほうだ、と。
◆
《この問題がすごくややこしくなってきたのは、いま起こっているのは、実は日本人が犠牲にならないかもしれない戦争の違法性の問題なんです。自分が死なない限り、戦争の合理性を否定するのは理念的には可能でも、やる気になる人は少ないっていう問題がある、これまでの平和運動は、日本人が犠牲になるからいけないっていう議論でした。世界核戦争の脅威という話ならそれでいいんですが、アフガニスタンやイラクに介入しても日本に住んでる人は死にません。で、自分が死なないと、戦争への関心も薄いんですよ。イラク戦争への反応で一番びっくりしたのは、戦争に賛成するのでも反対するのでもない、ただの無関心が日本で多かったことです。それがいまの一番苦しいところでしょうね》。
インタビュアー《語弊のある言い方ですけど、テロリストにすらなれないっていう、本当に容赦のない現実が……》。
藤原《容赦ないし、もっとリアルなんですよね。で、こういう〈貧乏人〉は、貧乏じゃない地域を攻撃して、脅威になったとき、初めて問題として自覚されるわけですね。もうずーっとむかしからそうで、〈貧乏人〉は怒らないときは無視されるんですよ》。
◆