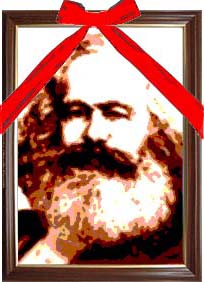
御会葬の皆様へ
*
不況の原因には大きく二つの見方がある。一つは、日本の市場が不完全だから健全な競争ができず、そのせいで不況になっているという見方。この場合、因習的な経済システムが悪いのでそれをなんとしても正せと主張する。小泉内閣の掲げる構造改革はこの立場だ。もう一つは、有効需要の不足からくるデフレによって景気が落ち込んでいることのほうが、それより深刻だという見方。最近よく目にするリフレ派の言い分はだいたいこれだろう。この場合、ネックは供給ではなく需要の側にある。「とにかく金を使わず貯めておく」という気分が日本中に行き渡ってしまったことが、問題の根本というわけだ。そうなると景気を刺激してデフレをインフレに転じさせることが何より先決だが、それができるのは政府や日銀しかない。すなわち財政や金融の政策だ。個々の企業や個人は今どうあがいても無駄ということになる。
同書は、アダム・スミスおよびケインズという経済学の基本の基本を解説しつつ、上記二つの見方が学説としてどのように対置しているのか、まずは素人向けに整理整頓する。そして著者自身は「有効需要不足」という診断と「財政金融政策」の治療を支持する(その立場を「貨幣的ケインジアン」と呼ぶ)。したがって「構造改革主義」は誤りだと考える。それらの論拠もすっかり提示する。
*
しかしこれだけなら、この本は半分の分量ですんだだろう。ところが同書は、「貨幣的ケインジアン」と「構造改革主義」の対比に「マルクス主義」を絡めてくる。あれまあ今どきマルクスとは。なんでわざわざ。ところがこれが関係大なのだった。マルクス経済学者の多くが、奇妙なことに、弱肉強食ともいうべき構造改革主義に限りなく近づいてしまっている(例:金子勝さん)。逆に言うなら、構造改革主義を分析すれば、そこにはマルクス経済学者の苦しくも捩れた本音が現われる。いや私自身、不況対策などを考えたり、朝生で金子勝氏の意見を聞いていて、なんだかぐずぐずと態度を決めかねるところがあったのだが、それももしやマルクス主義に由来していたのか?(うすうす気づいていたものに、いよいよ向き合わされたというべきか)。
ではなぜ、マルクス主義は構造改革主義に加担してしまうのか。それには深いわけがある。深すぎて素人がフォローしていくにはさすがに面倒くさい。しかしフォローすればするだけ味わいもまた深い。著者の示すところによれば次のようになる――
マルクス主義は80年代にレーガンや中曽根の発想だった新自由主義にはっきり反対した。一方、構造改革主義は、具体策としては市場原理主義に近く、したがって新自由主義に近い。ところが今のマルクス主義は、新自由主義に反対したようには構造改革主義に反対できない。その背景は何か。マルクス主義はケインズ的な政策を国家独占資本主義とみなして批判してきたが、構造改革主義もケインズ(貨幣的ケインジアン)とは不況の診断と治療をめぐって対立する。つまりマルクス主義は、敵(ケインズ)の敵(構造改革主義)に対してついガードが甘くなっているというのだ。もうひとつ。構造改革主義は日本型経済システムを悪と見る。この点はマルクス主義と一致する。しかしそうだとすると、80年代の新自由主義にもマルクス主義は同じ理由で接近してよかったように思われる。ところがそうはしなかった。当時のマルクス主義は、新自由主義にも、新自由主義の敵であるケインズ政策にも、まとめて反対していた。要するに大ざっぱだった。大ざっぱですんだのは、新自由主義が日本型経済システムと本気で格闘したわけでもなかったからだ。いわばまだノンキな時代だった。ところが構造改革主義は、日本型経済システムに本気でメスを入れようとする。つまり、これまでマルクス主義が「日本型経済システム×」「市場原理主義×」と深く考えずに主張していたところへ、一応深く考えた構造改革主義という新しい勢力が「日本型経済システム×」「市場原理主義ほぼ○」を引っさげて出現してきたのだ。マルクス主義は虚を突かれた。「日本型経済システム×」に目をくらまされて構造改革主義に引きずられ、しかもケンイズ憎しの心情があって離れがたく、とどのつまり「市場原理主義×」を明快に主張できなくなっている、というわけだ。
――う〜む、波乱万丈の国取り物語だ(フォローできただろうか)。こうした構図を著者は「左翼のはまった罠」と言い表す。少し角度を変えて分かりやすく述べた部分を、さらに引用しておく。
《八〇年代から九〇年代前半くらいにかけて、「日本型企業社会」が閉鎖的で不公平だという左翼の議論を前にして、ぼくがずっと感じていた違和感は、つまるところ「その閉鎖性を壊すということは、すべての労働者を厳しい競争と不安定な雇用・処遇にさらすということか?」というものであった。/オルタナティヴとしての社会主義の像が不鮮明な時代、いくら「それは違う」と力説しても、結果的にはこうした主張は「新自由主義」に絡めとられてしまうだけなのではないか、と。こういう違和感はもちろん、多くの左翼シンパに共有されていたと思う。しかしその先の議論が詰めてなされることは、ほとんどなかった。それが、九〇年代後半以降の「構造改革主義」に対するガードの甘さにつながったのであろう。》
*
さて、財政金融政策によるデフレ解消が先決と考える著者は、構造改革主義には否定的なのだが、それは単に今の不況に適さないという判断だけではない。さらに見過ごせないのは、構造改革主義の主張がモラリズムの調子を帯びていることだ。構造改革主義は、この不況はどこかに悪いやつや怠け者がいるから起こる、個人の努力が足りないから起こる、と考える。しかも、将来のためというより、バブル経済という過去の罪に対する罰として痛みを負わせたいなどと望んでしまう(そもそも著者等によればバブル経済の是非は判定できない)。
おまけに、この「変革のためには痛みに耐えろ」という態度は、そもそも資本主義の残酷さを指摘してきたマルクス主義とは相性が悪くないらしい。《もちろん、これはまず第一に、資本主義の不正と人間性を告発する意味を有していたが、反面このマルクスの知的遺産は一種の劇薬であり、結局市場経済の採用が避けられないと観念したマルクス主義者を、オーソドックスな市場経済礼賛主義者以上に極端な市場モラリズムへと追いやる傾向を持つ。つまり転向した元マルクス主義者は、「市場経済の下で発展したかったら、いろいろつらいことに耐えなければならないよ」とのお説教をともすれば垂れたがる、ということである。》かくして構造改革主義とマルクス主義は、モラリズムといういっそう厄介なアマルガムを形成してしまった。揚げ句に飛び出した迷言がこれだという――「下手に景気が回復したら構造改革が遅れる」。
*
そうなるとしかし、マルクス主義者は今や、市場経済というものを、まさか本気で礼賛しているのか、それともやっぱり内心は頑なに拒否しているのか、まったくどっちなんだと言いたくなる(どっちであってもヘンなのだけれど)。しかしマルクス主義者はともかく、私はどうなのだ。あなたはどうなのだ。資本主義、市場原理、結果としての富の不平等。○なのか、×なのか。
経済というものをめぐるこの究極の問いは、実はこの本全体に貫かれている。著者は慎重に思考を重ねたうえで「市場経済が正当な手続きを経ているかぎり、結果としての不平等は限度内において容認できる」という立場を取る。ただしそのとき、不平等は「弱肉強食」と「共存共栄」に分けて考える。市場経済はそもそも共存共栄のシステムだが、弱肉強食のサバイバルゲームに陥ることもあると言うのだ。そして、人々を弱肉強食に追いやる代表こそが不況なのだと強調する。だから今の不況の対応としても「完全雇用の実現を通じた弱肉強食の回避と共存共栄の実現を」と結論する。逆にこの観点からみると、モラリズムにまみれた構造改革主義や転向マルクス主義は、市場原理を共存共栄の手段ではなく自己目的化してしまっている。ここにこそ、構造改革主義に傾いた政治家・経済学者・市民に対する、著者の根源的な非難があるようだ。
《もともと左翼は、「市場社会は共存共栄である」という自由主義者の主張に欺瞞をかぎつけ「それは幻想で、実態としては弱肉強食だ」と告発してきたのだが、いまや「市場社会は弱肉強食で、それは逃れがたい現実だ」と勘違いして、居直る奴らが出てきたのである。これこそが、いまの左翼にとって最悪の敵であるはずなのに、このままでは敵の土俵に乗せられて、返り討ちに遭うのがおちだ。もう少しデリケートな議論を行わねばならない。》
*
この「弱肉強食か共存共栄か」の観点は、「自由か平等か」「機会の平等か結果の平等か」といった対立で言い切れなかったものを、初めて捉えられるかもしれないと著者は言う。この思考の極みは独創的だと感じた。そして、不平等ということについて、なお執拗に問う。市場経済のいわば同義として生じるような不平等は認めるしかないが、それでも「不平等それ自体が悪い」とは言えないのかと。《それが整合的で実現可能なヴィジョンであるかどうかはともかく、なぜそのような感覚がかくも強固にあるのか? そこにはなお何らかの真理が、「三分の理」があるのではないか?》と。
この要請から、マルクス主義の根幹が改めて検証されることになる。構造改革主義の検証が同書第一のピークだったとすれば、これは後半の山場だ。「貨幣の存在論」「搾取理論」「歴史の発展段階論」「疎外論」と、まさにマルクス主義の総まくり(この元のテキストがウェブサイト『Hot Wired Japan』に掲載されたとき、実際「総まくり」と言ってように記憶する)。したがって読み通すのもなかなか大変だ。でもまあ『資本論』を読み通すことはどうせ一生なさそうだし、せめてこれくらいはということでどうだろう。得るところはぺージ数に増して絶大。
で、その中身はすっかり省略するわけだけれど、著者はマルクス主義の役割を評価しつつも、社会主義や共産主義に未来はないこと、資本主義を受け入れざるを得ないことを事細かく論証していく。ずぶの素人としては、マルクスと弟子たちの関係をキリスト教成立のアナロジーで捉えたり、共産革命を終末思想とみなしたりするところが、やはり絶妙だった。後書きで《かくしてようやっとぼくはマルクス主義を「野辺送り」にし》たと呟くが、実際そのとおり厳かに念入りに死化粧が施され荼毘に付され埋葬され別れの言葉と合掌――。
でもちょっと待てよ。冒頭にあげた不平等論はどうなった? たしかに搾取理論のところで《…それは労働者と資本家の間の経済格差、不平等の説明のロジックとしては使えても、その不平等を批判し告発する議論としては、あまりうまくいかない、と言わねばならない。》とは書いている。しかし「不平等それ自体は悪くないのか」という問いが、この章できっちり答えられたようには見えない。よってこの点は後日蒸し返すとしよう(というか墓の掘り返し?)
*
ところで、同書はなぜかサイエンス・ウォーズの話から始まる。経済の本なのにどうしてと思っていると、自然科学に対するポストモダン思想の錯誤という図式が、経済学においても当てはまるのだと言う。ポストモダン思想は、自然科学が自然科学のパラダイム自体を問うていないと批判して一定の成果を上げたが、それに絡んで学問としての勇み足も生じた。このポストモダン思想の源流であり、錯誤や勇み足の源流でもあったのは、むろんマルクス主義だ。考えてみれば、マルクスの『資本論』は経済学であると同時に外部からの経済学批判として特異な価値を持った。それはポストモダン思想が自然科学に自然科学批判を促したのと同じような価値だ。しかしマルクス主義も、それに絡んで経済学としての実効を失いやがて錯誤に陥った。まさに同じ図式。ポストモダン思想が自然科学に対する錯誤だったとすれば、マルクス主義は、同書が解説する新古典派経済学に対する錯誤ということになる。こうしたモチーフは意外に広く強く浸透していたのだろうか。いわばそのようなベースキャンプから、しかし単独でこの探求に踏み込んだのが稲葉振一郎だった。
したがって、『経済学という教養』という名の一冊が、マルクス主義についてこれほどの考察をしたのは、なにも不況対策としての勘違いを咎めたいだけではなかろう。マルクス主義の誤りは、経済を含めたまさに教養全般に関わるのだ。同書が、素人とはいえサイエンス・ウォーズ等にも興味のある「人文系読書人」を読者として名指ししたのは、そういうことだ。教養の新しい展開というものが今あるなら、ポストモダン思想ないしはマルクス主義の旧弊を脱することなくしてはありえない、とまで断じていいのかもしれない。言い換えれば、マルクス主義は批判の力も錯誤の力も莫大なのだ。同書の射程もどこまでも深くなりうる。
マルクス主義者を自認する人は、この本をどう読むのだろう。私は自分がマルクス主義者だとは思わないが、20世紀の生まれとして考え方に影響を受けていないはずはない。「なんちゃってマルクス主義」的な発想は、無意識のうちに付きまとい、それが様々な現実の難問を避ける逃げ道として機能したこともあっただろう。少なくともそこはいよいよ改心したほうがよいのか。著者自身マルクス主義には複雑な思いを抱えてきたと言う。だから同書は、個人がマルクス主義の磁場を脱していった思考体験をそのまま伝えようとした、と見ることもできよう。
この不景気に対して貨幣的ケインジアンの政策がどれほど正解となるか。そこはまさに素人の私にはなんとも言えない。しかし、マルクス主義というものに関しては、その主義を捨てるかどうかは別にして、たとえば同書をひもときながら自分の胸に手を当ててチェックしてみることは、まさに不可欠なのだ。構造改革主義やマルクス主義の人たちが、そうした反省の機会を一度も持たないでいたら、日本経済は、あるいは日本の教養は、またもや新たな10年を失うことになりかねない。
*この本に沿った感想はここまで。
日本の不景気。これはいったい誰のせいなんだ。「誰のせいでもありません」。我が社はいかに頑張るべきか。「いえ頑張れることは何もありません」。そりゃ困るよ。誰かがどこかでズルしてるから景気が悪いんだろう、そいつらをやっつけなきゃ。そのために我が社だって痛みに耐えているんだ。そうじゃなきゃ困るよ! 「なぜ困るのですか」。……はあ?「誰も悪くなくて、あなたも痛い思いなどしなくていいなら、それに越したことはないじゃありませんか」。たしかにそうなのだ、べつに困ったり悩んだりしなくていいのだ。ところがなぜか我々はそれでは気が収まらない。犯人を探したがり、自らを痛めつけたがる。なぜだろう。やはり小泉総理の「構造改革!」のスローガンに引っ張られているのか。ところが、話をさらにややこしくしている黒幕がいるらしい。それは意外や意外、マルクス主義なのだった。稲葉振一郎『経済学という教養』は、不況対策として唱えられる複数の経済学説を分析していくなかに、未だ根強いマルクスの影その全貌を克明にさらしていく。
しかし先に言ったとおり、「不平等」をめぐる問いが私のなかに渦巻いている。
それは後日、この本を受けた考察として書いてみたい。(続く)