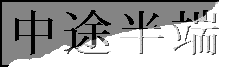
[本文]
ある朝、通勤のために家を出てすぐ、この言葉が浮かんだ。そうか、わかった。早い話が、ことごとく中途半端なのだ、私は。すべてはこれにつきる。自分のこれまでと今とを一気に説明する言葉が見つかったような気がした。
その日は昼前に暇時間ができたので図書館に入り「群像」を手に取った。高橋源一郎の「日本文学盛衰史」である。読む。衝撃。天から啓示が下ったような。そのまま全文コピーした。といっても60円だ。100円玉でおつりがくる。安いねえ、きょうびの最高水準小説は。
今回は、二葉亭四迷の言文一致体が国木田独歩の目を覚まさせた経緯を綴っている。それまで独歩は何かを感じて書こうとすると、たとえば「宇宙茫々、窮まりなきを見る。其間に生滅する此人類これ何ぞや」という風になってしまった。本当は違った言葉で違ったことを言いたいのではないかと疑問が浮かんだ場合でも、やはりそのようにしか書けなかった。また、そのようにしか感じなかったという。
しかし、今の僕たちなら「嗚呼吾生まれて人間となり、来たりて此世に住み、住みて此時代に遭ひ、」などと、絶対に口をついて出てくるわけがない。こんな奇妙な言い方、本当に昔はおかしいと思わなかったのか。
この疑問が解けたのは明くる日。昔の学生運動を写したビデオをたまたま見た時だ。出る人、出る人、みんなが例のアジ演説口調なのだ。今から見れば笑ってしまう。でも当時はそれが普通だった。大マジだった。そういう口調で政治と革命を思い、そういう口調で語っていた。 らしい。
明治の文語体と学生運動のアジ演説口調。いつの世にも、文体という一種の特異なパラダイムが、それが特異であるという意識を持たれぬまま潜行しているのか。
ビデオの時代からだいぶ下って、僕が学生のころでも、まだ拡声器を持つ人々はいた。彼らは普段の会話でも、たとえば「学生の要求がさあ」と言うような時に、「ヨウキュウ」という語を「ウ」から高くなる平板型のアクセントで発音すべきところを、たいてい頭の「ヨ」を高めた特異なアクセントで話したのを覚えている。あれはアジ演説口調の名残だったのか。逆に最近の青年諸君においては「カレシ」に代表される平板化が、なし崩し的に普及せんとするは、これ奇矯。如何なる作用なりや。
さて「日本文学盛衰史」をコピーまでしたのは、これだけのことではない。
文語で表現しつつ「どうもおかしい」と密かに首をひねっていた国木田独歩は、二葉亭四迷が言文一致体で翻訳した「あひびき」を読み、「そうか、これだあ!」と目の前が開けたという。
(ここから引用)
今なら、ぼくはこの世界を抱きしめることができる。
(略)
作家たちは各々の言葉と共に遠くへ行こうとしていた。「内面」というものが、いま自分が書いている場所にないなら、探し求めるしかないからであった。そして、それぞれの場所で作家たちは「内面」を見つけたと喧伝した。当人はそう信じたが、やはりそれは証明のできないことだった。経験はいつも個人に属し、ほんとうのところ、その個人の経験を他人は理解できないからだった。それは言葉を使って探し求める他ないのに、言葉を使うことによって、それは一層遠ざかっていくのである。
(引用ここまで)
この、文語体でしか表現できない明治作家たちの苦悩を書いたくだりを読んで僕は、またもやウィトゲンシュタインが、とりわけ永井均が感じたところのウィトゲンシュタインが、このページに光臨したかと思ったのである。
しかし、これを機に大喜びで創作に励んだ独歩は、結局また行き詰まる。
だがその結果こそ「語れえないものについては沈黙するしかない」と書いたウィトゲンシュタインの、「語りえない」ことの中身や技術ではなく、語りえない原理そのものを浮かび上がらせているように思えて深い溜息をつく。
今僕もまた、ここまでに述べたことのエッセンスをできれば伝えたいと思っているが、なかなか難しい。まあそれは語りえない原理によるというよりは、単なる力量不足である可能性が大きいが、それでも少し書く。
誰かが何らかの言葉を文字に綴ったり声に出したりすると、それを見聞きした人の気持ちや行動になんらかの作用が及ぶ。そういう作用こそが「言葉のハタラキ」あるいはウィトゲンシュタインによれば「言葉の意味」であると言うわけだ。しかし、その「言葉のハタラキ」自体を言葉でぴたっと説明しようとしても、それだけは原理的にできない。え、なんでと訊かれると、それこそ説明がややこしくなるのだが、言葉を使えばイヤでも何かが伝わってしまうこと、つまり言葉によって起こる作用を絶対コントロールできないことが関係する。と思われる。
そこらあたりの秘密にずっとこだわったのが、ウィトゲンシュタインであったし、二葉亭四迷であったらしいし、かつ高橋源一郎であるようだと僕には思える。
ついでに「言葉」を「私」に置き換えて考えてみる。
私という存在は、実は必ずや社会に実現してしまう。どんな風に社会に出ていこうと、私という存在が周囲になんらかの作用や伝達を起こしてしまう。それが意図したものと違う時「こんなの、私の理想の生き方じゃない」「私のやりたかったことはもっと別のことだ」と嘆く。しかし「理想の生き方」とは「私が私そのものであるような生き方」ということだとすると、それは原理的にできない。ような気がする今日このごろである。そのものの本質は、そのもの自体によっては決して表わされないのだ。
難しいのでこのへんで。どんなやり方で私を実現しようとしても私は決して実現しない。常に中途半端にしか感じられないのが宿命なのだ。
以上全部でまかせです。←あぶりだし(おまけ)
中途半端。
独歩はそう思った。