『言語的思考へ 脱構築と現象学』
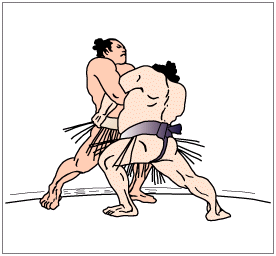
ポストモダン思想の流行とは、こんなふうなことだったのではないか。
ところが今ごろになって、「それは本当かい?」と問いかける大人がやってきた。竹田さんだ。「言葉と意味がしっくりこない? 言いたいことがうまく言えない? たしかに全体の理屈はそうだろう。でも実際のところはどうなんだい。君(この言葉)は、あの親(あの意味)が、本当に赤の他人だと思ってるわけ? ようく見てごらん。どうみたって君の親じゃないか」。静かに諭す。
『言語的思考へ 脱構築と現象学』(竹田青嗣)は、そういう本だ。
デリダの言語理解が言語の実情をとらえていないこと。さらにはポストモダン思想全体が思想の本質を外していること。竹田はそうした根本的な批判を本格的に行う。その方法はというと、フッサールの現象学を使う。実は、そもそもデリダが『声と現象』で、悪の黒幕たる西洋形而上学に連なるとして否定したのが、フッサールの現象学だった。しかし竹田は、デリダの現象学理解のほうが間違っていたのだという。そんなわけで、「現象学」を乗り超えたはずの「脱構築」をさらに乗り超えるため、ふたたび「現象学」が呼び寄せられるのだ。
千秋楽結びの一番、物言いがついて取り直しとなりました、というぐあいか。デリダの戦法は「猫だまし」「肩すかし」に「送り出し」だったが、竹田はがっぷり四つに組んでそれを封じ、じりじり「寄り切り」を狙う。
デリダによれば、意味とはつまるところ差異でしかない。だから「言葉は、どうにもわからない」。しかし現象学によれば、そうはならない。竹田は、フッサール先生さらにはハイデガー先生(実存主義)の教科書を引っ張りだしつつ、図解もしつつ、「ほら、ちゃんとわかるでしょ」と頑張る。さらに、デリダは形而上学を批判したけれど、このデリダの言語理解、および「絶えず世界に異和を唱えつづける、そして異和の根拠を空無化しておく」というポストモダン思想自体が、そのまま形而上学の落とし穴に嵌まっていたのだ、といった分析をする。
その結果(この本を読んだ結果)どうなるかというと、言語の謎というやつが、あっさり解消される。しかしそれは、謎がぱんぱんに膨らんで華々しく飛び散るのではない。しゅわしゅわしゅわと萎んで落ちたという感じ。「なんだ、がっかり。田舎に帰って、父ちゃん母ちゃんに孝行でもすっぺかな。まあ、あの間抜けな顔は、たしかにオイラに似ているわなあ」。風船おじさんが天高く舞い上がったというファンタジーを信じていたいけど、実際は海に落ちたに決まってるけどね、といった寂しい思い。
しかし今、どちらかに軍配をあげようとは思わない。それより、デリダの脱構築とフッサールの現象学、ともに理解が進んだし、どちらもとても面白いと感じた。とりあえずこれは正直な感想だ。
竹田さんは、伊達や酔狂で哲学しているのではない。まじめにこつこつ、社会や人間の可能性と変革を考える大人。この本からはその姿勢が伝わってくる。デリダの革新性を認めないのではなく、最大限に評価している。しかし、そこで戯れてばかりの青年(の晩年)には「いつまでもそれじゃ埒があかないよ」と分別を示すのだ(ラチというなら、哲学の国から拉致された主観や作者を、奪還したのが竹田さん?)。
だが、この懇切丁寧な説明も、青年にとっては「大人はわかってくれない」かもしれない。あるいは、「つまらん! おまえの話はつまらん」と、大滝老人にソッポを向かれるかもしれない。生き急ぐ若者やこらえ性のなくなった年寄りに、大人の哲学は持ちこたえられるのか? 岸部一徳さんの誠実な表情が、竹田さんの表情に重なる。
◆
以下、ちょっと難しげ。
さて、この本は、最後に向かうにつれて、次のようなことを徐々に大胆に断じていく。
――デリダ、ドゥルーズ、フーコーに代表されるポストモダン思想は、近代が作りあげた市民社会・資本主義・国民国家というものを、ちゃんと批判できていないからダメです――。
ちゃんと批判できないのはなぜか。竹田さんによれば、ポストモダン思想を基礎づける「形式論理的な思考」というやつが、ちゃんとした思考ではないからだということになる。「形式論理的な思考」とは、「Aの絶対性を批判するために非Aを想定する」、そういう二項対立的なやり方のこと(ポストモダン思想こそが二項対立を克服しようとしたという見方もあるようだが、それはそれとして)。では、この思考だと、どうダメなのか。
《形式論理的思考は、その二項対立的特質によってつねに世界を潜在的に価値のあるものと負のものに大きく分節する。またそれは論理矛盾を作り出して帰謬論的に敵対する項を否定することで、自項の正しさを相対的に証明する(*おまえの理屈はおかしいじゃないか。だからおれは正しい)。だから自己の正当性を積極的に提示する必要がない。》
《…その基本構想は、現にある社会、国家、イデオロギー、制度性に対して、新しい対立項の原理を導入、対置することでその「正当性」を相対化、無根拠化するという方法によって支えられている。》
《こうしてポストモダン思想は、思想としてすでに信念補強的性格を帯びていたことが分かる。何が解体すべき対象であるかが予め前提されていたのだ。》
たとえば、相撲というスポーツをあたまから否定したいので、あえて相撲の本質に迫ることはせず、代わりにプロレスの素晴らしさばかり語る、という感じだろうか。はじめから相手の土俵に登る気はなく、かといって独自の土俵を作り上げもせず、相手の土俵下からちょっかいを出すだけ、という感じだろうか。
ところで、ちょうどこの本を読んでいるとき、「反戦落書き」の一件が報じられた。そのせいか、被告側の主張に、なんだかこの「形式論理的な思考」っぽさを感じてしまった。それは「落書きの取り締まり方がおかしいがゆえに、落書きはおかしくない」といったふうな理屈だ(直接そう述べているわけではない)。まあしかし、あの一件について、このことだけを強調しようとは思わないので、この話はもう終わり。
ともあれ、竹田さんは、こんなやり方のポストモダン思想は、ちゃんとした哲学ではないとまで言う。じゃあ、ちゃんとした哲学とはどういうものか。詳しい説明は省くけれど、結局カントやヘーゲルに代表される近代の哲学こそが、「形式論理的な思考」ではない、ちゃんとした哲学だったのだ、というところに落ち着く。
そんなわけで、この本の最後の最後はこうだ。
《現代思想は、それがヘーゲル=マルクス主義のドグマ性と見なしたもののうちに、現代の克服すべき形而上学を見出した。ヨーロッパの啓蒙的理性と合理主義的知性、論理(*ロゴス)中心主義、ヨーロッパ的普遍主義、そういったものこそ二十世紀になって激しい矛盾を露呈したヨーロッパ的原理の"根拠"だと考え、この形而上学性を克服することに新しい思想の課題があると考えた。しかしこの考えは、哲学の思考の本質的な原則を踏み外していた。現代の哲学者や思想家たちは、総じて近代哲学が残した原理的思考の重要な功績を理解せず、むしろ近代市民社会原理、近代国民国家、そしてそれらを支える共同体原理の内破と顛倒という時代的動機に押されて、形式論理的批判思想を作り出した。それは従来の最高価値を批判し顛倒することはできたが、しかしもっと重要なこと、つまり新しい「原理」を構想できず、この弱点を補填するために思考の超越的ジャンプを行なうほかなくなっているのである。こうしていまや、二十世紀的思想の役割は終焉しつつある。われわれは、もう一度、哲学の本質的思考の原理を再構築し直さなくてはならない。その方法原理をわれわれはこの論考の中ですでに輪郭づけてきたのであり、いまやそれを十全に展開させるべき場面に立っている。》(*「従来の最高価値」に傍点)
ここでいう「展開」が、竹田さんの公式サイトにある「戦争抑止の原理」などに示されているのだろう。あるいは、『群像』8月号の長い論文も気になるところだ(未読)。
くりかえすが、「ポストモダン思想はあまり正しくない」「近代はあまり間違っていない」、そういう主張である。ただ興味深いことに、どうやら竹田さんの力点は、「ポストモダン思想はあまり正しくない」よりも「近代はあまり間違っていない」のほうにあるみたいなのだ。つまり、市民社会・資本主義・国民国家は、それほどひどいものではないんじゃないの、という立場。それがかえって新鮮、というか古鮮というか。
◆
私は、近代の真価も、ポストモダン思想の真価も、したがって竹田さんの真価も、まだよくわからない。
ただ、竹田さんの話から、哲学には二つの役割があるのかなと思えてくる。1つは、哲学を抽象的で一般的な理論のまま磨きあげること。もう1つは、哲学を具体的で個別的な現実に当てはめて鍛えあげること。で、竹田さんは後者に重きをおく。
しかし、複雑多岐にわたるこの現実に対して、総合的な原理を見出し、実際の思想として試作し改良し、それを政治や経済や文化に(あるいは言語関係にも親子関係にも)実装して機能させる――、そこまですべての作業に、哲学は責任を持て、とまでは言えないだろう。もしも竹田さんがこれを全部一人でやろうとしても、それは無理がある。
だから、哲学が、いわば現代数学のように「抽象的で一般的な理論をそのまま磨きあげる」役割に徹するというのも、アリではないかと思うのだ。現代思想は、その役割は、ちゃんと果たしたのではないか。
いやそれどころか、現代思想は、現実社会でそこそこ具体的に個別的に実践されてきたようにも見える。ああ、だから、「でも、その実践は生半可だった。それはその哲学が生半可だったからだ」というのが竹田さんの見解なのか。それに対して「でも、哲学というのは、どれも抽象的な理論にすぎなくて、具体的な実践としてはどうしたって生半可なのではないですか?」と問うこともできる。すると竹田さんは「いや、そうではない。たとえば現象学は生半可ではない。もちろんカントもヘーゲルも生半可ではなかった。近代は生半可ではない」ということになって、話が元に戻りそうだ。
このへんで。
*上下のイラストは『大相撲ホームページ』にあるのを黙って使っている。
大人の寄り切り
言葉と意味の関係を、折りあいの悪い親子に喩えてみよう。そのとき「親子なんて断絶して当然さ。そのきずなに根拠などないんだから」…てなぐあいに先導もしくは煽動したのが、デリダさんだった。それを聞いて青年たちは沸きたった。「やっぱり! オイラもそう思ってたんだよ。こうなったら家出だ。暴れるぞ。あんな親どうせ他人じゃないか」。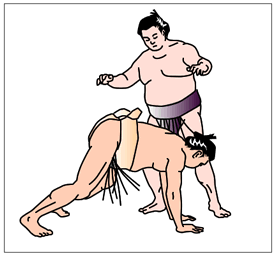
*Copyright(C)2001 Nihon Sumo Kyokai All Rights Reserved. Copyright(C)2001 NTT-X. All Rights Reserved.