堀江敏幸著(新潮社)
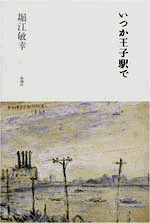
『いつか王子駅で』は、タイトルに惹かれて読み初めたものの、うすうす予想していたとおり、時事や流行といった香辛料の刺激はまったく漂ってこない。したがって、「シブ知」以外にどんなスタンスで相対すればいいのか、見当がつかない。表紙がまた、荒川界隈の古い風景画とかで、いかにも地味----つまり常磐響の装丁などとは正反対。小見出しもなく、各ページにまさに文学然として並んでいる活字全体が、どうにもモノトーンだ(当たり前)。で、腰巻きがない。こういう時に限って線引きもない。
1964年生まれの作家の近作、であるはず。なのに、昭和に書かれた中堅作家の小説と言われても通ってしまいそうだ。はたして最後まで興味が続くかな、というのが正直な気持ちだった。まあたまには芥川賞かつ三島賞の作家のご威光にでもあやかろう、といった信心に支えられなければ、じきに降りていたかもしれない。
しかし、結論を言おう。「今まで私はどんな料簡で小説を読んでいたんだろう」である。11章あるうちの、3章めぐらいで、すっかりハマっていた。
モノトーンに見えた文章は、克明に「塗り絵」していくような読書を生みだしたのだった。塗り損じも塗り残しもまったくなし。細かい輪郭で丁寧に線引きされている物語の展開と文章の綴りは、各章ごと、また書物全体を通して、その彩りや遠近を鮮やかに浮かび上がらせていく。塗り終えて眺めれば、すべての展開は有機的である。発酵しない文章は一つもない。
職人による薫陶、とでも言いいたい。
実際、職人と呼べる人物が幾人か登場する。ある大工は鉋(かんな)の仕事について次のように述べる。
《木の善し悪しだとか刃の研ぎぐあいとか、・・・・、いろいろな要素が調和してはじめて美しい削り屑ができる。その日の気温とか湿度とかで感触の変わってくる木の肌を読んで、その微妙な変化を、刃の出し方や力の入れ方や挽くタイミングといった経験値から割り出した勘という方程式にあてはめてみる。物をつくるひとはみんなそういう指先の、指の腹の感覚を研ぎ澄まして、皮膚一枚の感触に心と神経をくだいている。だから薄い削り屑がいちばん大事な判断材料のひとつだ》
これは、この小説を削り出していく営みについても、ぴったり当てはまる。
さらに私は妙なことを思った。この書物の各ページに律義に並んでいる活字たちは、もしやこの美しい削り屑の方ではあるまいかと。逆に、削られて出来たはずの何ものかは、我々が削り屑を通して想像することによって、ようやく姿を現わすのだと。
では、このように美しい削り方は、いかにして可能か。別の旋盤工が言う。
《最近はホームセンターだのなんだの材料も道具もおあつらえ向きのまがい物が揃ってるからみんな誤解しているようだが、金物屋で出来あいの道具を買ってきてなにかを作ろうったって、そんなものは根本からして寂しい。本当に斬新なものってのは、それを作るための斬新な機械が必要なんだから》
斬新な文章には、斬新な道具が、斬新な機械が不可欠である、と。
この斬新な道具や機械というものを、我々が手にするとしたら、それはやはり文章としてであろう。実のところ小説としてであろう。たとえば『いつか王子駅で』もまた、ホームセンターの既製品ではない、斬新な文章を削る斬新な道具として機能するに違いない。
『いつか王子駅で』、愛すべき一冊。「近ごろ芥川賞を受けた作家に読むべきものなどない」という命題が、必ずしも正しくない大事な反証である。そう思いたい。もしもあらゆる芥川賞作家がこれほど素晴しいのであれば、短い人生に全部を読まねばならず、大変困ったことになる。堀江敏幸は特別なのだと思いたい。
それとも、このように正統としか思えない文学こそ、腰を据えて怪しむべきなのだろうか。どうなんだろう。
いずれにせよ、正しい読みとは、きっと、《普段どおりにしていることがいつのまにか向上につながるような心のありよう》こそがもたらしてくれる。しかし、それはひどく難しいのだと、人生の職人である正吉さんは呟く。
《変わらないでいたことが結果としてえらく前向きだったと後からわかってくるような暮らしを送るのが難しいんでな》
図書館本の弱点としては、勝手に傍線が引かれたりする以外に、腰巻きのないことが挙げられる。キャッチコピーという愛想のいい客引きなしで、ひとり黙って読みに入っていかねばならないのだ。