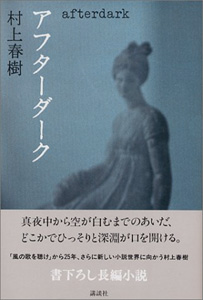
抽象問題の抽象解決
深夜のファミレスに19歳の少女マリが一人でいて本を読んでいる。そこに、一度会ったことのある高橋という青年が偶然やってきて同席する。マリはことごとく思わせぶりな態度だ。人生に対してなにか特別な拘りを抱えているふう。ところが、それが実際どういうものかは分からない。ぐずぐずと先延ばしされる。だいぶページが進んで、ラブホテルを管理するカオルという人物との会話から、家に帰りたくなくて夜を過ごしているのだという、ベタな言質だけは取れる。そしてもう終盤になって、別の人物コオロギとの会話のなかで、マリは姉のエリについて悩んでいるのだと、これも拍子抜けするほど予想を下回る事実だけが口から出る。といっても早い話が「昔はわかりあえた姉と、今はわかりあえない」ということで、ありふれた悩みというしかない。その姉のエリは、ひたすら眠り続けるという不思議な症状にとらわれているのだが、それをマリがどう受けとめているのかの核心も、今ひとつ不明瞭だ。
そもそもマリは姉の理解という点であまりに具体性を欠いている。
《「私の場合、正直言って、姉のことはよく知らないんです」とマリは言う。「彼女が毎日どんなことをして暮していたとか、どんなことを考えていたとか、どんな人とつきあっていたとか。悩みがあったかどうかさえ知りません。(…)」》
「でもこっちはもっと知らないんだから、わかることをもっと教えてほしいね。話はそれからじゃないか」と私は思う。
一度は一体感が持てたのに、その後どんどん遠く離れたとも言う。そして《何がいけなかったのか、私にはわからない。》わかれ。間違ってもいいからわかれ。姉と話せ、姉に聞け。そして読者にヒントをくれ。そうすれば私もまた間違ってもいいから何か言えるのに。
マリは家に戻って、眠っている姉のベッドにも入るのだが、《マリはベッドに身を起こし、指先で頬の涙を拭う。何かに対して――それが何なのか具体的にはわからないのだけれど――ひどく申し訳ないような気持ちになる。自分が取り返しのつかないことをしてしまった、という気がする。》「何か」には傍点が付いている。でもなおさらそれが何かは私にはわからない。最後までこの調子だ。何か大事なことがあります、それが何かはうまく言えません、でも読者のみなさんはわかってくれますよね、と。
《マリはふと思う。私はこことは違う場所にいることだってできたのだ。そしてエリだって、こことは違う場所にいることはできたのだ。》なんだか朝のテレビの星占いみたいじゃないか。そうだマリは一度細木数子に見てもらったらどうだろう。「あんた、何か悩みを抱えているわね。ひょっとして家族に関すること? 当った? ああ、お姉さんのことね。昔はわかりあえたお姉さんが、今は心が離れてしまったと。そうでしょうそうでしょう、そう出ています。あのね、いいですか、お姉さんとの思い出を大切にしなさい。そうすれば、全部うまくいきます。」
高橋は、マリの姉エリと同級生で、エリのことが気になっている。そして高橋は妹のマリにも惹かれだす。高橋にとってエリとマリはそれぞれ大きな謎なのだ。
謎がそこにあったら解こうとおもうに決まっている。相手がなにやら深刻そうで、しかも二人きりでいるのだから、一から聞かせてもらおうかなと思う。いや、高橋がというより読者がそう思う。マリがボストンレッドソックスのキャップを被っているとか、高橋がファミレスのチキンサラダが好きとか、そういう説明を少々我慢しつつ聞かされているのだから、そろそろマリの心境みたいなものをズバリ説明してくれよと言いたい。しかしすでに述べたとおり、マリは具体的には喋らない。高橋もあまり聞かない。というか村上春樹がそうしない。でも高橋はエリとマリのことを知りたい、できれば助けにもなりたいと思っているんだから、とことん聞いたら、と突っ込みを入れてしまう。そうしなきゃ始まらないじゃないか。
ともあれいろいろあって、マリと高橋が未明の街を歩くシーン。
《「……ねえ、少し歩かない?」とマリは言う。
私もとくに感想を述べたり質問をしたりする気が失せる。
《「たくさん歩いて、ゆっくり水を飲めばいいいのね」
どっちでもいいんなら、私もこれ以上語ることはない。
マリと高橋
…そうですか。
二人ともいかにも村上春樹の小説の登場人物だなあと感じる。それにしても、全体に、なんというか、ぬるい、ゆるい。「都会の孤独な生」とでもいった紋切り型のムードだけが膨らんでいく。単なる未熟さゆえに意味をぼかして大袈裟にしてみた嘆きというか呟きというか、悩みを悩んでそれを楽しんでもいるかも、といったレベルの、実にしょうもないぬるさ、ゆるさとして受け流してしまいたくなる。
いや、ことさら崇高で重大な打ち明け話を期待しているんじゃない。実際の渋谷で夜を明かす普通の若者だって、そうするだけの身も蓋もない、くだらない、しかしとても切実な理由がそれぞれあるだろうと思うのだ。マリはそういう普通の少女として描かれているわけではないが、その程度の詳細でいいのだから尋ねて答えさせろと思ってしまう。もどかしい。思わせぶりな少女を渋谷のデニーズやすかいらーくという具体的な場所に配置して、それでも少女の事情や性格は鮮明になった気がちっともしない。
小説では一つの事件が起こり、マリがそれに巻き込まれる。事件というのは、深夜勤務の途中だったサラリーマンがラブホテルに行き、そこに呼んだ中国人の娼婦を殴って怪我をさせ、衣服や小物をすべて奪って置き去りにする、というもの。その張本人である白川の会社での仕事ぶりや、タクシーでの帰宅、自宅に戻ったあとの早朝のキッチンの様子が描かれていく。しかし、買春をし暴行をした白川の動機や反省はとくに明かされることはない。
この身勝手な仕打ちは、白川のなんらかの現実の反映であり結果であるのだろう。そうした結果として現れた買春や暴行については、通常の感覚で理解できる。ではその原因となる白川の具体的な現実とは何だろう。しかしそれは語られない。こんな具体的な結果をもたらした原因のほうはもっとずっと抽象的なものだった、というのだろうか。
ラブホテルを管理する元女子プロレラーのカオルも、従業員のコオロギとコムギも、いずれも強烈に個性的な人物として登場するが、でもけっきょく内実がない。彼女たちがそうである必然性というものが感じられない。それともそういうものを求めるほうが間違っているのか。
登場人物について、実際の日常をあえて曖昧にしその切実さもわざわざ減じさせるような表現ばかりで描写していく。これは村上春樹の大昔からの特徴だろう。フォトレタッチの「ぼかし」をかけたような効果。いや、生活や性格をぼかすのはかまわない。我々は自分の苦境に少々「ぼかし」をかけないとたまらない。現実をいつもいつも直視などできない。でもマリの状況や心情に「ぼかし」をかけているのは、マリ自身だとは言えない。どちらかといえば、「ぼかし」をかけているのは、この小説の世界を俯瞰する視点であり、その世界では神でもあるはずの村上春樹だ。しかしその「ぼかし」をかけた責任は、「私たち」という人称を読者と共有することで、いつのまにかごまかされているようで、妙な気分だ。
いやもちろん、具体的なものや現実的なものを語るつもりが最初からないのなら、それはそれでOK。村上春樹の問題意識やマリやエリや高橋の問題意識が、こういうふうに抽象性としてしか実相を表せない類いのものなら、それはこのように語るしかない。でも実際のところ、マリは単に姉のことで悩んでいるじゃないか。ほんとは具体的なことを抽象的にぼかすことによって、解決への努力をしないことを合理化しているだけではないのだろうか。
こういう語り方は、作家自身、登場人物たち、読者それぞれに具体的である問題が、抽象的な次元においては必ず出会えるし必ず一致するだろう、といった確信から来ているのかもしれない。それが好きかどうかは人それぞれだが、私はもう飽き足らなくなってきた。都会の孤独な生といったこと以上に、もっと強いもの、深いもの、そうしたリアルな共感を誘うかというと、疑問だ。もっと具体的な困難をもっと具体的に語ってほしい。じつは『国境の南、太陽の西』あたりから、ずっとそう思っている。もしも村上春樹が私の友人で、一緒にファミレスでお茶でもしているんだったら、作品についていやというほど具体的に質問するに違いない。
それでいて音楽のタイトルなどはあいかわらずやけに具体的だ。《イヴォ・ポゴレリチの演奏する『イギリス組曲』》とか。これがこうも具体的である必然性はないように思える(この作品にかぎったことではないが)。それより、たとえばマリの父母がどんな生い立ちでどんな仕事をしているのかのほうが、有益な情報のように思えるのだが。
あるいは、高橋はコンビニで買う牛乳の種類や日付を常に吟味する。それがモラルだとまで言う。10〜20年くらい前は、我々はなんとなくそういう拘りを楽しんでいたかもしれない。でも今はそれほどではない。いくらか社会や他人と具体的に関わるのなかでのモラルを見つけたい気がしている。「ここでこの曲をかけるのは、理由があるけど、理由はいわないけど、きみはわかってくれるよね」といった調子のよさ。しかし、世の中は今それほどゆるくない。ぬるくない。いや私自身は本当は、もっとゆるいぬるい世の中が好きだ。心から好きだ。だが今の世の中はどうもそれとは真逆の方向に行っているということに、さすがに気づいている。
ファミレスというと、映画『パルプ・フィクション』が思い浮かぶ。あそこで強盗をやらかすカップルは、いかにも未熟で見るに見かねてしまうが、それはつまりそのような切実さ、愚かさをひしひしと伝えてきたということだ。阿部和重の「鏖(みなごろし)」もファミレスにこそふさわしい酷い出来事を描いていたと記憶する。
それに比べてマリは、あるいはカオルもコオロギも、強い個性を持っているようでありながら、共感できるだけのおぞましさがそこから匂ってこない。その代わり、それぞれに虫のいい、一人よがりの、弱い夢想という感じが否めない。
村上さん、もっとドストエフスキーみたいに詳しく書いてくれ! だってあなたは、日本中の読者が黙っていてもこぞって読んでくれる作家なのだ。そのような恵まれた関係に乗って、今回もまた本一冊分の言葉を独占的に伝送しているのだから。でも、でも村上さんはやっぱり、妥協や手抜きとかではまったくなく、すべてこうやるしかなくてこうやっているのだろう、こうなっているのだろう。それに関してはずっと信頼してきたし、今後も信頼するだろう。だけど共感はもうしないかもしれない。
さてさて、マリの姉エリはなぜかベッドでこんこんと眠り続けている。するとその部屋のテレビモニターに不可解な映像が現れる。中には一人の男がいてエリをじっと見つめている。そのうちに男はいなくなり、今度はエリがモニターの中に入り込んでいる。マリの眠り、それに伴う異次元のような存在、そこへの出入り、これらはこの小説の最大の問い、最大の謎というべきだろう。
《テレビはこの部屋への新たな侵入者である。もちろん私たちだって侵入者ではある。しかし私たちとは違って、新たなる侵入者は静かでもないし、透明でもない。中立的でもない。それは疑いの余地なくこの部屋に介入しようとしている。そのような意図を直観的に感じ取る。》
こうした場面のこうした説明を、読者は以後くりかえし読んでいくことになる。では最後になって確実に納得できるところに達しただろうか。なるほどと理解できたこと共感できたことがあっただろうか。う〜ん、いろいろ難しいことなら言えるのかもしれないが、易しく言うなら、ない。眠り続けたりテレビに閉じこめられたりするエリの状況は、要はなんらかの比喩や形容ということになるのかもしれない。しかしそれが何の比喩か何の形容か、ヒントでもいいから、やっぱりもうちょっと具体的に示されないかぎり、対処しようがない。かりに自分が友人から相談を受けたとしてみよう。「オレさあ、毎晩眠っているあいだ、テレビに閉じこめられてるみたいなんだよ。もうどうにも出れなくて困っちゃうんだ」。彼が友人ならば、それってどういうことか、もうちょっとちゃんとした説明を求めると思う。自分なりに実感できるまで質問すると思う。それが無理なら「いいから、もう帰って寝たら」と突き放すしかない。
モニターの中でもがいているエリの様子。《混乱し戸惑いながらも、その場所を成立させている論理や基準のようなものを、なんとか把握し、呑み込もうと、全力を尽くしている。その気持ちはガラス越しに伝わってくる。》
伝わってくるか、ほんとに? いかにも深淵な謎が存在し、それをいかにもわかれと言いたげなのだが、けっきょく謎は謎でしかない。もちろん、「人生楽ありゃ苦もあるさ」とか「にんげんだもの」といった文言にも、心を揺り動かされ人生すら変わってしまう場合もあるのだから、そのような公理というか恒真式というかそういう類いの真理なら、この小説も提供してくれているのかもしれないが。
そのくせ医師にはあっさり言われたらしい。《自分で『これからしばらく眠る』と宣言して、そのまま眠っているわけで、心がそれほど眠りを求めているのなら、しばらくゆっくり眠らせてあげるしかないんじゃないかと言われました。》
まるで雅子妃の「適応障害」だ。我々だって仕事なんか行きたくなくって、それでも無理やり行かざるをえなくって、心を痛め体を傷めるのだ。それはみんな会社や学校への「適応障害」だ。だったら今すぐ休め、辞めろ。いや私は常にそう主張してきたし、ときどき実践もしてきた。だが、そんなこと言ってられない世の中の実情こそ、もっと克明に描写してくれよ。みんながみんな雅子妃やエリのように恵まれてはいない。
エリの眠りについてコオロギの理解も――
《「あのね、私にはもちろん詳しいことはようわからんけど、お姉さんはなんか大きな問題を、心の中に抱え込んでるんやないかな。自分一人だけの力ではどうにも解決のつかんようなことを。そやから、とにかく布団に入って眠り込んでしまいたい。とりあえずこの生身の世界を離れてしまいたい。その気持ちは私にもわからんでもない。というか、身につまされてよくわかるよ」》
なんか大きな問題を心の中に抱え込んでる? そりゃそうだろう。これもみんなそうだ。だから我々だって、許されるなら毎朝もっと布団に入って眠り込んでいたい。
そもそもエリに対して、語り手である「私たち」は基本的にどういう立場か。
《残念ながら(というべきだろう)浅井エリに対して、私たちにできることは何もない。繰り返すようだが、私たちはただの視点なのだ。どのようなかたちにおいても、状況に関与することはできない。》
まあ、たしかにできないだろうさ。我々一人ひとりが固有に抱え込んでいるこの困難、この悩み。それは誰も聞いてくれないし、ましてや誰も小説に書いてはくれない。もちろん直接解消もしてくれない。それでも、設定されたある他人のお話を辿ってであっても、そうした我々の困難や悩みにどうにか到達できたかなと感じさせてくれるのが、文学というものではないか。そのためには、そこにある設定、エリであれマリであれ白川であれ、もっと踏み込んで直視して愚直に説明する姿勢が大事なのではないか。現実の我々はそれぞれ、自分にもっと具体的に踏み込んで具体的に苦しんでいる。
そして、
いやほんと、今にもそうなってしまいそうな気配だ。でも実際のところ、無ばかりでもない。狭すぎるけれどまだ自分の場所はある。解体されない意味もある。世界は完全に隔てられてはいないのだ。感覚は完全に沈黙してはいない。そこに賭けようと我々はまだ真剣に思っている。
そんなふうに考えてくると、登場人物の言動に、いちいち物足りなさや調子のよさが目につくのだった。
マリ
段ボールハウスみたいにと言うけれど、ここには自分が段ボールハウスの住人になるかもという想像が欠けているのではと思った。何に喩えようとそれは勝手だが、逆に、喩えられたほうの段ボールハウス自体は、村上春樹は何に喩えることができるのだろう。もちろん私にも段ボールハウスは想像しかできないが、それでもこうした比喩にはたぶん使わないだろう。段ボールハウスはもっと具体的な物質で、きっとそれほどヤワじゃないぞとも言いたくなる。
コオロギ
う〜む。広告ちらし、哲学書、エッチなグラビア、一万円札、たしかにどれもただの紙切れかもしれないが、どれも一様な紙切れではない。私にはそれぞれの価値は明らかに違う。どれも役に立つが、みな一様に役に立つのではない。どれもくだらないものではあるが、みな一様にくだらないのではなく、それぞれの陰翳や色彩を伴ってくだらない。そのことを分別して考えることが、現実に対処するということなのではないか。
白川(自宅に帰ってキッチンで)
「何か」というけど、それは娼婦をラブホテルで殴り身ぐるみはいで捨ててきた、さっきの出来事のことだろう。それを「何か」なんて抽象的に思うか? 「何か」なんて抽象的に書くか? もちろん円高や母子の心中もいろいろな「何か」の一つにすぎないさ。そんなふうにニヒルになることは我々はしょっちゅうだ。テレビは騒ぎすぎだといつも思う。しかし、そうした出来事の中にしか、我々を取り囲むこの世の中の実相は現れてこない。そうした具体的な出来事に痛く感じ入る自分の感覚を通してしか、世の中を問うことはできないじゃないか。丸焦げになった自動車とか言われれば、イラクのテロなども思い浮かぶ。たしかにイラクははるかに遠いと思っている。それでもイラクはどこか切実に私の問題だとも思う。それに比べたら、マリが眠らなければならない問題などは、私にはそれほどのことではない。なんでもかんでもごっちゃにしてシニカルにふるまいたくはない。
白川のやったことは、中国人の娼婦を殴って置き去りにしてきたことだ。それは通常、一番どうでもよくない問題だろう。
《「逃げ切れない」と男は言う。「どこまで逃げてもね、わたしたちはあんたを捕まえる」》
書籍の帯にここが引用されていた。白川は、娼婦から奪った携帯電話を、なぜか帰宅途中にコンビニの棚に放置した。しばらくして同じコンビニにやってきた高橋が、その携帯電話を見つける。すると娼婦を派遣している組織から電話がかかり、白川に告げるつもりの上の台詞を、高橋が代わって耳にすることになるのだ。
白川のモラルは、もちろん高橋が引き受けることはできない。白川に引き受けさせなければ、不公平だ。
「逃げ切れない」といった抽象的な言葉は、やはり占いみたいなもので、誰にだって当てはまる。でも各自が何から逃げ切れないのかというと、それはもっと具体的でだ。だから各自は各自の逃げ切れない課題と向きあうしかない。白川の問題を高橋が分かち合うことも処理することもできない。電話では「わたしたち」という言葉も使われている。わたしたちっていったい誰だ、と高橋は考える。たとえばここで、地震や戦争の死者を想像していいのかもしれない。でもそれはファンタジックにすぎる。地震や戦争の死者ほどかどうかは知らないが(それはわかるはずがない)、高橋は高橋なりに、私は私なりに、それぞれ逃げ切れない困難を抱えている。
この殴られた中国人の娼婦を、マリが世話をし、話も聞いてやることになる。彼女が自分と同じくらいの年であることにも驚く。マリは中国語を学んでいて北京に留学する予定だという。そのくせ本当は中国へ行きたくなんかないともいう。なんだかバカにした話だ。中国は具体的にリアルに存在するのだから。マリのことはもうべつに詳しく知りたくなくなった。それよりラブホテルで殴られた彼女のことのほうが、もっと知りたい気分だ。あるいは、その中国に最近たった260円の時給を求めて日本から働きに行くという具体的な人のことなら、もっと知りたい。
エリについての記述。
その努力を村上春樹は本当にしているのだろうか? わかりやすい言葉に置き換えるのが簡単ではないことは知っているが、みんなそれでもどうにかコミュニーションを試みている。そうしなければなおさら伝わらないから。もちろん伝えたいものが本当にあるかどうかは問題ではない。伝わるという状態がそこにいくらかでも成立するかどうかが問題だ。それもみんなうすうす承知しつつ、それでもいろんな場面で(家で、学校で、会社で)本当に苦労して言葉を使っているのだ。それはけっして抽象的な問題ではない。
たとえば求人のある企業に出向いて、自分の経歴や能力を買ってもらう。ああなんとくだらない話だろう。しかし履歴書や面接では、その能力や経歴を、実にくだらないけれど、自分にではなく相手にわかる言葉に置き換えてみなければ始まらない。村上春樹はもう履歴書も名刺もいらないだろう。みんな知っている。みんな過去の言葉(小説)を記憶してくれている。だから何も言わなくても、それどころか曖昧に隠そうとしても、煙に巻こうとしても、周囲が必死で推察してくれる。そういうのも文学かもしれない。でも、そういうものでないからといって、文学でないわけではない。だからやっぱり「もう少し具体的に書きましょうね」と作文の先生に言われても、仕方ないのではないか。
さてこの小説は、都市を大きく俯瞰した描写から入る。それらを「私たち」という人称で眺めていることを、冒頭からあからさまにする。
そして小説の中で、あちら側に行ってしまったエリが、結局小説の終りには、無事こちら側に帰還する。抽象的な悩みは、抽象的に解決された?
そして「私たち」の視点はふたたび上空高くのぼっていく。もう都市は動きだしている。
《様々な色に塗られた通勤列車が思い思いの方向に動き、多くの人々をひとつの場所からべつの場所へと運んでいる。運ばれている彼らは、一人一人違った顔と精神を持つ人間であるのと同時に、集合体の名もなき部分だ。ひとつの総体であるのと同時に、ただの部品だ。》
そうか、ただの部品か… (私は絶対そうは思わないが)
阪神大震災があった日、ヘリコプターで上空から実況をした筑紫哲也が顰蹙をかったのを思い出した。
《しかしやがて、エリの小さな唇が、何かに反応したように微かに動く。一瞬の、一秒の十分の一くらいの、素早い震えだ。しかし研ぎすまされた純粋な視点としての私たちが、その動きを見逃すことはない。この瞬間的な肉体の信号を、私たちはしっかりと目にとめる。今の震えは、来るべき何かのささやかな胎動であるのかもしれない。あるいはささやかな胎動の、そのまたささやかな予兆であるのかもしれない。》
…多事争論でした。
このあいだ昔の会社の同僚たちと飲んで、けっきょく朝まで過ごし、ファミレスで始発を待った。みなそれぞれに困難に立ち向かっていた。ある者はストレスのせいで心身がボロボロになりまる一ケ月病床にふせって最近会社に復帰したばかりという。ある者は映像の仕事をしていながら本質的な思索の果てにとうとうテレビ受像機を家から捨ててしまったという。ある者は飲み屋を出た直後あるビルの軒下にそのまま倒れ込んで起きようとしない。私はいったい、なんという会社で、なんという同僚たちと、日々を過ごしていたのか。そうした困難の一つ一つに私は具体的に触れたいと思った。それでどうなるものではない。でもそうするくらいしか生きることに意味はない。
そんなあの日の深夜のファミレスで、もしも隣の席から、マリと高橋やコオロギとの、あのようにぬるい、ゆるい会話ばかりが延々漏れ聞こえてきたとしたら、まったく歯がゆく腹立たしく感じてしまったのではないだろうか。
明け方になって、マリは高橋にいう。
そりゃ朝帰りの頭で話したって、あらゆる問題はそうなるのだ。ちゃんと眠ってまたこんど具体的に順を追って話してくれ。
ところで、私ももちろん、いつかいつかと先延ばししている問題は、いくつかあるように思う。では、いつかべつのときは、本当に来るのか?
それほど長い小説でもないのに、感想がこれほど長くなるのはちょっとおかしいんじゃないかと思いつつ、このさい村上春樹についてずっとわだかまっていたことを、洗いざらいぶちまけることになったのは、よかったかもしれない。馬糞がたっぷりとつまった巨大な小屋、というつもりでは全然ないのだが…。
(1)マリのこと
(2)高橋のこと
(3)
「いいよ。歩こう。歩くのはいいことだ。ゆっくり歩け、たくさん水を飲め」
「何、それ?」
「僕の人生のモットーだ。ゆっくり歩け、たくさん水を飲め」
マリは彼の顔を見る。奇妙なモットーだ。でもとくに感想も述べず、質問もしない。》
「そうじゃなくて」と彼は言う。「ゆっくり歩いて、たくさん水を飲むんだ」
「とくにどっちでもいいみたいだけど」
高橋はそれについて頭の中で真剣に検討する。「そうだな、そうかもしれない」
二人はそれ以上何も語らない。》
《「でも、どうしてあなたは私に興味を持つわけ?」
「さあ、どうしてだろうな? 今のところ僕にもそれはうまく説明できない、でも、君とこれから何度か会って話をしているうちに、フランシス・レイの音楽みたいなのがどこからともなく流れてきて、どうして僕が君に関心を抱くのか、具体的な理由をずらずらと並べるかもしれない。雪だってうまく積もってくれるかもしれない」》
(4)白川のこと
(5)村上春樹のこと
(6)ファミレスにからめて
(7)エリの眠りの謎について
《ブラウン管の光が次第に薄らいでいく。それは小さな窓のかたちに四角く縮小し、最後には完全に消滅する。あらゆる情報は無となり、場所は撤収され、意味は解体され、世界は隔てられ、あとには感覚のない沈黙が残る。》
(8)ほか気になる台詞
《「時間をかけて、自分の世界みたいなものを少しずつ作ってきたという思いはあります。そこに一人で入り込んでいると、ある程度ほっとした気持ちになれます。でもそういう世界をわざわざ作らなくちゃならないっていうこと自体、私が傷つきやすい弱い人間だってことですよね? そしてその世界だって、世間から見ればとるに足らない、ちっぽけな世界なんです。段ボール・ハウスみたいに、ちょっと強い風が吹いたら、どっかに飛ばされてしまいそうな……」》
《「人間ゆうのは、記憶を燃料にして生きていくものなんやないのかな。その記憶が現実的に大事なものかどうかなんて、生命の維持にとってはべつにどうでもええことみたい。ただの燃料やねん。新聞の広告ちらしやろうが、哲学書やろうが、エッチなグラビアやろうが、一万円札の束やろうが、火にくべるときはみんなただの紙きれでしょ。(…)大事な記憶も、それほど大事やない記憶も、ぜんぜん役に立たんような記憶も、みんな分け隔てなくただの燃料」》
そしてマリに、お姉さんのこともいろいろ思い出せばそれが大事な燃料になるから頑張れと励ます。
《身体はたしかな疲労を訴えているのだが、頭の中に、彼を眠らせまいとするものがある。何かがつっかえているのだ。その何かをうまくやり過ごすことができない。白川はあきらめてまた眼鏡をかけ、テレビの画面に目をやる。鉄鋼の輸出ダンピング問題。急激な円高の是正についての政府の対策。母親が二人の幼児を道連れに自殺した。車の中にガソリンをまいて火をつけた。丸焦げになった自動車の映像。まだ煙が立っている。街ではそろそろクリスマスの商戦が始まっている。》
(8)言葉をちゃんと使っているのか
《彼女が今やろうとしているのは、自分の目がそこで捉え、自分の感覚がそこで感じていることを、少しでも適切な、わかりやすい言葉に置き換えることだ。その言葉は半分は私たちに、半分は自分自身に向けて発せられることになる。もちろん簡単な仕事ではない。唇は緩慢に、とぎれとぎれにしか動かない。まるで外国語を話すときのように。すべてのセンテンスは短く、言葉と言葉のあいだに不均一な空白が生じる。空白がそこにあるはずの意味を引き延ばし、薄めていく。こちら側にいる私たちは懸命に目をこらすのだけれど、浅井エリの唇がかたちづくる言葉と、彼女の唇がかたちづくる沈黙を見分けることすらむずかしい。》
(9)俯瞰する視点
《私たちはその予兆が、ほかの企みに妨げられることなく、朝の新しい光の中で時間をかけて膨らんでいくのを、注意深くひそやかに見守ろうとする。夜はようやく明けたばかりだ。次の闇が訪れるまでに、まだ時間はある。》
(10)私ごとのアフターダーク
《「ねえ、悪いけど、やっぱりまだうまく話せないみたい」
「疲れているし、頭の中が整理できない。それに、自分の声が自分の声みたいに聞こえないの」
「いつかでいいよ。いつかべつのときに。今はその話はよそう」》
(11)